|
|
高校受験の受験パターン
高校受験 倍率 偏差値一覧 高校受験情報の詳細はこちら
このページでは高校受験の受験校の組み方(受験パターン)についてお話します。
まず、第一志望校を決めることから始めます。
第一志望校が決まったら、それを軸に受験校を組んでいきます。
高校受験での1人あたりの受験校の数ですが
一番少ない人でも2校、多い人だと10校くらいになります。
平均的には3〜6校くらいになります。(東京の場合です)
受験校を組む場合、
「おさえ校」「実力相応校」「挑戦校」を満遍なく入れることが大切になります。
「おさえ校」とは、自分の学力なら確実に入れる学校。
「実力相応校」とは、普段の実力が出せれば合格できる学校。
「挑戦校」とは、自分の実力よりもレベルが高い学校。
偏差値で考えると自分の偏差値が60なら
「おさえ校」が偏差値50くらいの学校
「実力相応校」が偏差値60くらいの学校
「挑戦校」が偏差値70くらいの学校になります。
この考え方は中学受験、高校受験、大学受験の全てに通用します。
多くの人は、第一志望校が挑戦校になるのですが、
中には、第一志望校が「おさえ校」や「実力相応校」レベルの学校だということも
あります。この場合、1、2校受験して終わりというケースが多くありますが、
せっかく一生に一度の受験ですので、よりレベルの高い学校を受験することを
お勧めします。また高い目標をもった方が結果的に成績UPにつながります。
というのも、例えば、偏差値60くらいの学校を目標に勉強すると、
どんなに良くても偏差値60までの力しかつきませんが
偏差値70くらいの学校を目標に勉強すれば、仮に偏差値70に届かなくても
偏差値65くらいにはなるものだからです。必ず「挑戦校」は入れましょう。
→「成績は」上がっていますか?「安い費用」で「確実に」成績を上げる勉強法はこちら
<スポンサードリンク>
さて、先程「おさえ校」「実力相応校」「挑戦校」を満遍なく入れることが大切
と言いましたがただ、偏差値だけを見て適当に決めるのはいけません。
特に、注意していただきたいのが「おさえ校」です。
「おさえ校」は俗に「滑り止め」と言われる学校ですが、
「滑り止め」だからといってあまりにも学力とかけ離れた学校を選ぶべきではありません。というのも、実際に行くことになってしまう学校になる可能性があるからです。
ですから、「おさえ校」は実際に通うことになったとしても納得できる学校を選ぶべきです。
中学生の中には、第一志望校の学校だけ見学に行って、それ以外の学校は受験当日まで行ったことがないなんていう人もいます。受験前は第一志望校の合格しか考えていませんから実際に第一志望校が残念な結果になったとき、初めて「おさえ」の学校を見に行って、こんな学校だとは知らなかったと後悔する人もたまにいます。
あたりまえのことですが、自分が受験する学校は全て、自分が学校見学に行き、
自分の目で見て確かめて決めることが大切です。
そしてもうひとつ大切なことは、
「おさえ校」はできるだけ早い日程で受験するということです。
まず最初に「合格校」を確保した上で、第一志望校に挑戦したほうが良いということです。
受験生の中には、はじめのほうの日程で挑戦校を受け続けて、全部上手くいかなかったら最後に「おさえ校」を受験するという人もいますが、この受験パターンは非常に危険です。このパターンだと「おさえ校」が「おさえ校」ではなくなります。
なぜかというと、普通の精神状態で受験すれば、簡単に合格できる学校でも、
第一志望校やその他の学校全てが不合格になったという状況で受験する場合には、相当のプレッシャーがかかります。このような精神状態では実力が発揮できません。また、相当にショックを受けた状態ですので、中には受験をしたくないというケースも出てきます。
ですから、なるべく「おさえ校は」早い日程で受験した方が良いと思います。
また「実力相応校」も必ず1校は入れるべきです。
受験生によっては、1つ「おさえ校」があるからそれ以外は全て挑戦という人がいますが、あまりにも実力とかけ離れている学校の挑戦は、何校受験したところで合格にはなりません。
受験生からしてみれば、たくさん受験すれば1校くらい合格するだろうという期待があるのですが、偏差値が10も離れている学校はまず合格できません。
最低、1校は納得のできる「実力相応校」を入れるべきです。
→「成績は」上がっていますか?「安い費用」で「確実に」成績を上げる勉強法はこちら
<スポンサードリンク>
では、具体的に「おさえ校」{実力相応校」をどう作るかですが、
まず「おさえ校」を作る有効な手段のは1つは
他校併願可能な私立の推薦入試を受験するということです。
どういうことかというと、本来、私立の推薦入試というのは単願推薦といって
合格したら、必ずその学校に入学しなければいけませんでした。
ただ、最近では、推薦入試で合格しても、他校を受験しても良いという学校が増えております。
さらに入学手続きも公立(都立の合格発表日)まで待ってくれるという学校もあります。東京都や神奈川県の私立の一般入試の解禁日が2月10日で、私立の推薦入試は1月の下旬ですから、ここで本番の前に「おさえ校」をつくることが可能になります。
「おさえ校」をつくるもうひとつの方法が
埼玉県の入試を受験するということです。
埼玉県の入試も1月下旬から始まりますので、ここで「おさえ校」をつくることができます。
(ただ、埼玉県の場合は、(地理的な面で)実際に通えるかどうかを考えましょう。
合格したけれど、実際に通えないのでは「おさえ校」をつくったことにはなりません。)
次に「実力相応校」ですが、これは第一志望校の日程によって変わります。
現在、東京の私立の入試日は2月10日、2月11日、2月12日に固まっています。
特に、ほとんどの私立は2月10日に試験を行います。ですから第一志望校が2月10日なら2月11日か12日に実力相応校を受けます。もしくは、2月の上旬に埼玉県や千葉県の学校を受験するという方法もあります。
そして、最後に都立ですが、都立は2月の下旬に入試が行われます。
先程も書きましたが、最後の都立を「おさえ校」にすることは極力避けましょう。非常に危険です。
また私立を第一志望校にしている人でも、都立受験は考えておきましょう。
というのも、最終的に第一志望校の私立に行けなければ都立に行くという人がけっこういるからです。都立の場合は、テストに「理科」「社会」もあるので、入試の直前になって、急に都立を受験するとなっても、「理科」「社会」の勉強が間に合わないケースがけっこうあります。
都立受験も計画に入れておきましょう。
一般の都立なら、ほとんどの学校が「当日の得点」と「内申点」の比率が5:5なので、
ある程度学校の成績で合否が分かります。
ですから、中学校の担任の先生との3者面談の際に学校の先生に提示された学校や
その学校にレベルが近い学校を受験校にしましょう。
また、進学指導重点校の都立なら、「当日の得点」と「内申点」の比率が7:3や6:4なので、
内申点が多少悪くても、筆記試験が得意な人は有利です。
さらに、進学指導重点校は問題が都立の共通問題ではなく各学校が独自で作った難しい問題なので、筆記試験、とくに難問対策をきちんとやっている人はレベルの高い都立を受験しても合格しているケースはたくさん見てきました。
以上が、受験パターンを組む際のポイントになります。
→「成績は」上がっていますか?「安い費用」で「確実に」成績を上げる勉強法はこちら
高校受験 倍率 偏差値一覧 高校受験情報の詳細はこちら
■絶対に中学受験で第一志望校に合格したい!!という方へ
<スポンサードリンク>
▲ このページのトップへ
>> 次へ(高校受験の受験パターン具体例)
▲ 受験勉強相談室トップページへ

高校受験・高校受験勉強・高校受験勉強法・高校受験の勉強法
受験校 志望校の決め方 受験校 志望校の選び方 高校受験の受験パターン
中堅私立高校受験 難関私立高校受験 進学指導重点校 都立高校 私立高校
高校受験の偏差値 高校入試の偏差値
高校受験の受験倍率 高校入試の受験倍率に関しては受験勉強相談室まで。
当サイト内の内容・画像の無断転載・転用については固くお断りします。
発見した場合、法的な措置を取らせていただきます。ご了承ください。
Copyright(C)2006 受験勉強相談室 All right reserved.
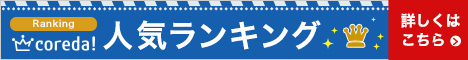
 |
|
 |
|

