進学指導重点校受験攻略法
都立高校とは……都立高校は大きく3つに分けられます。
進学指導重点校 ………東大・東工大・一橋大・京大・国公立大医学部・早慶上智など
の難関大学の合格実績を上げるために東京都から進学指導
を重点的に強化をするよう指定された高校
→日比谷 戸山 西 八王子東 青山 立川 国立
進学重視型単位制高校…進学指導を重視するよう東京都から指定を受けている単位
制高校
→墨田川 国分寺 新宿
普通の都立 ………上記以外の学校
また入試問題の形態に着目して分類すると3つに分けられます。
自校作成問題校 ………英語・数学・国語の入試問題を自校で作成している学校
(理科・社会は共通問題)
→進学指導重点校+進学重視型単位制高校
共通問題作成校 ………英語・数学・国語・理科・社会の5科目全て共通問題の学校
→上記以外ほぼ全て
一部自校作成問題校 ……3科のうち一部の科目だけ問題を自校で作成している学校
→国際(英語のみ自校作成問題。なお国際は3科入試)
普通の私立高校とは……偏差値55以下の学校。
(これは一般的な呼び方ではなく、このホームページ内においてのみの呼び方)
→「成績は」上がっていますか?「安い費用」で「確実に」成績を上げる勉強法はこちら
<スポンサードリンク>
進学指導重点校受験攻略法
高校受験をするには2つの方法があります。
1.一般入試
2.推薦入試
進学指導重点校も普通の都立も一般入試と推薦入試の両方を実施しています。
絶対に進学指導重点校に合格したいならば、一般入試と推薦入試の両方を受験するのが良いでしょう。
(これは普通の都立も同じです。)
ここで進学指導重点校と進学重視型単位制高校の募集要項をまとめてみます。
(選抜方法は各学校にリンクを貼ってありますのでそちらで確かめてください。)
進学指導重点校と進学重視型単位制高校+国際の推薦入試と一般入試の募集定員・選抜方法
|
推薦 |
一般 |
推薦選抜方法 |
推薦小論文 |
一般選抜方法 |
学力検査:調査書 |
自己PRカード得点 |
一般10%枠
(特別選考) |
|
男子 |
女子 |
合計 |
男子 |
女子 |
合計 |
| 日比谷 |
33 |
30 |
63 |
133 |
121 |
254 |
詳細 |
なし |
詳細1
詳細2 |
7:3 |
100点 |
○ |
| 戸山 |
33 |
30 |
63 |
132 |
121 |
253 |
詳細 |
○ |
詳細 |
7:3 |
100点 |
○ |
| 西 |
33 |
30 |
63 |
132 |
121 |
253 |
詳細 |
○ |
詳細 |
7:3 |
100点 |
○ |
| 八王子東 |
33 |
30 |
63 |
132 |
121 |
253 |
詳細 |
○ |
詳細 |
7:3 |
100点 |
なし |
| 青山 |
14 |
13 |
27 |
130 |
120 |
250 |
詳細 |
なし |
詳細 |
7:3 |
120点 |
なし |
| 立川 |
33 |
30 |
63 |
132 |
121 |
253 |
詳細 |
○ |
詳細 |
7:3 |
100点 |
○ |
| 国立 |
33 |
30 |
63 |
132 |
121 |
253 |
詳細 |
○ |
詳細 |
7:3 |
100点 |
○ |
| 墨田川 |
- |
- |
160 |
- |
- |
156 |
詳細 |
- |
詳細 |
- |
- |
- |
| 国分寺 |
- |
- |
96 |
- |
- |
220 |
詳細 |
なし |
詳細 |
7:3 |
100点 |
○ |
| 新宿 |
- |
- |
96 |
- |
- |
220 |
詳細 |
○ |
詳細 |
7:3 |
100点 |
○ |
| 国際 |
- |
- |
80 |
- |
- |
80 |
詳細 |
○ |
詳細 |
7:3 |
100点 |
なし |
※「国分寺」は小論文がない代わりに「パーソナル・プレゼンテーション」がある。
「国分寺」は一般試験において英数国が傾斜配点(1.5倍)また調査書は内申9科全て1倍
つまり、学力検査の得点は英数国の3科が450点満点、理社が200点満点で合計650点を700点に
換算する。調査書は9科で45点を300点に換算する。他の学校と大きく異なるので注意!!
※「国際」は英語のみ自校作成問題。また英語のみ傾斜配点。また調査書は内申9科全て1倍
一般試験で面接を実施。面接点は100点満点。一般試験は合計で1200点満点になる。
つまり英語120点満点、数国200点満点で合計320点を700点に換算する。
調査書は9科で45点を300点に換算する。なお自己PRカード、面接点がそれぞれ100点ずつで合計
1200点満点になる。
※推薦入試の募集定員は全体の募集定員の2割、一般入試の募集定員は全体の募集定員の8割の
学校が多い。
→なお一部の学校ではさらに一般入試の9割を総合成績(学力検査の得点+調査書+自己PRカード)
順で決め、残りの1割は学力検査の得点のみで決める学校がある。(特別選考)
(上記の表で一般10%枠が○の学校)
※推薦入試は各学校によって選抜方法がまちまち。
基本的には 「調査書+小論文(作文)+自己PRカード+面接」の総合得点順で決められる。
ただし、小論文や作文は実施しない学校もある。
小論文(作文)を実施する学校を受験する場合は対策が必要不可欠。適切な訓練をしなければ
高得点がもらえる小論文は書けるようになりません!!
※推薦入試 出願 1/24 試験日 1/27 合格発表日 2/2
一般入試 出願 2/6・2/7 願書取下げ 2/14 願書再提出 2/15
試験日 2/23 合格発表日 3/1 (H18年度入試)
都立の推薦入試は倍率が高く、実力があっても不合格になってしまう傾向があります。
進学指導重点校や進学重視型単位制高校の場合、さらに人気があり高倍率です。
ただ都立が第一志望校なら絶対に推薦入試から受けるべきです。
推薦入試と一般入試を両方受ければ2回チャンスがあるのですから。
推薦入試は非常に難しいので、合格はできないという前提で受験したほうが良いです。
ここで合格を決めてやる!!と意気込んで受験すると不合格だった場合のショックがあまりにも大きくなり
私立入試や都立の一般入試に悪影響を及ぼします。
→「成績は」上がっていますか?「安い費用」で「確実に」成績を上げる勉強法はこちら
<スポンサードリンク>
<推薦入試>
「調査書+自己PRカード+面接+小論文」(小論文がない学校もあります。)
の合計点で合否が決まります。
①調査書は5段階評価の数字ではなく
観点別評価(A・B・C)が得点化されます。
Aが何点、Bが何点、Cが何点というのは学校によって違います。上記の表の詳細のところに各学校への
リンクが貼ってありますのでご確認ください。
ですから、ただ内申の5段階評価の数字が良いだけではなく、観点別の評価でAがたくさんあった方が良い
ということです。
→対策としては、学校のテストの得点を良くするだけでなく、授業中の態度(積極性)や提出物など
もきちんとしなくてはいけない。(あたりまえのことですが)
②面接はあいさつの仕方や質問の受け答え方、よく聞かれる質問の
対応の仕方などを訓練する必要があります。
→中学校で校長先生や教頭先生などが面接の練習をしているところもあります。
また塾や家庭教師の先生にお願いするのも効果的。
なるべく身近にいない人(あまり親しくない人)とやった方が本番の雰囲気がつかめます。
③小論文を実施する学校を受験する場合は
小論文(作文)の対策が必要不可欠になります。
小論文・作文は書き方がきちんと決まっています。ただ適当に思ったことを書いても得点にはなりません。
感想文とは違います。実際、中学生に小論文を書かせてみると最初はひどい文章を書きます。
→対策としてはきちんと書き方を知ったうえで、その書き方に従って、
小論文を書く訓練をしないと高得点がもらえる小論文は書けません。
学校によって小論文の配点は異なりますが調査書の得点ではあまり点数の差が
つかないことを考えると、進学指導重点校の都立の推薦入試で差がつくのは
小論文の得点です。
つまり、小論文や作文を実施している学校の合否のカギを握るのは小論文の得点です。 対策をきちんと立てましょう。
<一般入試>
「学力検査+調査書+自己PRカード」(国際は+面接点)
の合計点で合否が決まります。
①学力検査(英語・数学・国語)は自校作成問題です。
進学指導重点校や進学重視型単位制高校の入試問題は普通の都立の共通問題に比べると
難しくなっています。3科目共通していえることは、中堅私立高校や難関私立高校レベルの3科
の勉強をしていないと合格点を取るのは難しいと思います。
特に数学に関しては、学校の成績が良かったり、学校の教科書の内容が分かっているだけでは
絶対に自校作成問題で合格点は取れません。
なぜなら
(1)自校作成問題では、記述(考え方や計算過程が分かる途中式)を書かせる。
(2)自校作成問題では、高度な証明問題が出題される。
(3)自校作成問題では、高度な作図の問題が出題される。
(4)自校作成問題では、文章の長い文章題が出題される。
↓自校作成問題のサンプルはこちら↓
日比谷の自校作成問題 戸山の自校作成問題 西の自校作成問題 八王子東の自校作成問題
青山の自校作成問題 立川の自校作成問題 国立の自校作成問題
墨田川の自校作成問題 国分寺の自校作成問題 新宿の自校作成問題 国際の自校作成問題
これらの内容は学校の授業ではあまり時間を割いて扱いません。かといって普通の教科書ガイドレベルの
参考書や問題集で勉強しても合格点は取れるようになりません。
これらの傾向にあった勉強をする必要があります。
>>数学の応用問題の鍛え方はこちら
②学力検査と調査書の比率は7:3です。
普通の都立なら調査書が非常に重要で合否の半分を決めてしまいますが、
進学指導重点校や進学重視型単位制高校は、調査書(学校の成績)より、学力検査を重視しています。
これは、大学入試の合格実績を上げるために
「難しい問題に対応できる生徒を学校が欲しているからです。」
ですから、進学指導重点校に合格するには、難しい問題を解けるよう訓練することが
最重要事項になります。
問題のレベルは先程申し上げたように、中堅私立高校や難関私立高校の問題とかわりがありません。
出題形式が特殊なことを考えるとそれより難しい場合もあります。
確実に数学で合格点を取るためには、
①中堅私立高校レベルのパターン問題を解けるようにする。
②進学指導重点校の自校作成問題の傾向(上記に挙げた4つ)に慣れる。訓練する。
③難関私立高校レベルの問題を解き、さまざまなバリエーションの問題に触れる。
→「成績は」上がっていますか?「安い費用」で「確実に」成績を上げる勉強法はこちら
<スポンサードリンク>
>>数学の応用問題の鍛え方はこちら
↓基礎力から応用力まで家庭学習で身につく「Z会」その秘密は...詳しくは↓
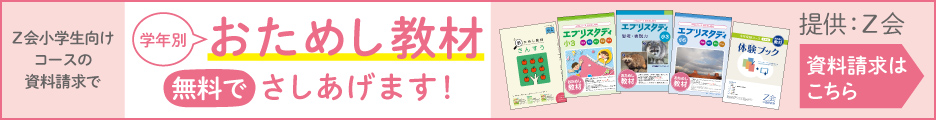

▲ このページのトップへ
<< 前へ(難関私立高校受験攻略法)
>> 次へ(普通の都立・私立高校受験攻略法)
▲ 受験勉強相談室トップページへ

高校受験・高校受験勉強・高校受験勉強法・高校受験の勉強法
受験校 志望校の決め方 受験校 志望校の選び方 高校受験の受験パターン
中堅私立高校受験 難関私立高校受験 進学指導重点校 都立高校 私立高校
高校受験の偏差値 高校入試の偏差値
高校受験の受験倍率 高校入試の受験倍率に関しては受験勉強相談室まで。
当サイト内の内容・画像の無断転載・転用については固くお断りします。
発見した場合、法的な措置を取らせていただきます。ご了承ください。
Copyright(C)2006 受験勉強相談室 All right reserved.
|

